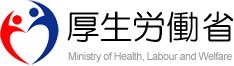■ 水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン 質疑応答集(Q&A)
平成30年3月27日公開,令和7年2月28日最終更新(Q4-4-2およびA4-4-2を追加)
環境省水道水質・衛生管理室 国立医薬品食品衛生研究所
(本ページのPDF版はこちら )
)
4. 妥当性評価の方法
- Q4-1) 「検量線の作成方法(上限、濃度点、回帰式の算出方法等)のみ変更した場合は、検量線の評価のみ行えばよい」とあるが、検量線の作成方法を変更した場合、添加試料の評価結果も変わると考えられるが、添加試料の再評価は不要か。
- A4-1) 妥当性が評価された検量線を用いて添加試料の評価を行っており、評価目標に適合していれば、その後で検量線の妥当性が確保できる範囲で検量線の作成方法を変更したとしても、添加試料の評価結果が目標に適合しなくなる可能性は低いと考えられるため、評価は不要である。添加試料の評価結果が大きく変わると考えられる場合は、添加試料の再評価を行う。
- Q4-2) 「検量線の作成方法に影響しない部分のみ変更した場合は添加試料の評価のみ行えばよい」とあるが、具体的にはどのような場合が該当するか。
- A4-2) 採水時に残留塩素を除去するための試薬や、試料の前処理方法(固相カラムの種類や試料の濃縮倍率)等を変更した場合が該当する。ただし、標準液も試料と同様に前処理を行う検査法の場合は、前処理方法の変更により検量線の作成方法に影響するため、検量線の評価も行う必要がある。
- Q4-3) 測定条件を変更した場合、例えばカラムの温度や流速、質量分析における定量イオン、キャリアーガスやパージガスを変更した場合は、検量線と添加試料の両方の評価を再度行う必要があるか?
- A4-3) 分析装置の測定条件の変更は、感度、ピーク形状等に影響を与え、定量結果にも影響を与える可能性があるため、検量線と添加試料の両方の評価を再度行う必要がある。ただし、機器のチューニングは測定条件の変更には該当しない。
- Q4-4) 「試験操作や試験環境の変化が生じない場合(検査担当者の変更等)は、再度評価を行う必要はない」とされているが、検査室を移転した場合は、妥当性評価を再度行う必要があるか。
- A4-4) 原則としてSOPに変更がなくとも妥当性評価を再度実施する必要がある。検査結果に影響を与えるおそれがない場合に限り評価を省略することができるが、移転前と比べて装置性能が同等以上か、試験環境に由来するブランクレベルが十分に低いかどうか等を確認してから判断する必要がある。
- Q4-5) 妥当性評価を行う際に、告示法で規定されている空試験及び連続試験を実施する場合の措置は必要か。
- A4-5) 必要ない。
妥当性評価された検査方法等の一部を変更した場合に必要となる評価について,表1に整理した。
表1. 妥当性評価された検査方法等の一部を変更した場合に必要となる評価
| 変更箇所 | 具体的な事例 | 必要となる評価 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 検量線の作成方法のみ | • 検量線濃度の上限、濃度点、回帰式の算出方法等の変更 | 検量線の評価のみ | 妥当性が評価された検量線を用いて添加試料の評価を行っており、評価目標に適合していれば、検量線の妥当性が確保できる範囲で検量線の作成方法を変更したとしても、添加試料の評価結果が目標に適合しない可能性は低いため |
| 検量線の作成方法に影響しない部分のみ | • 採水時に残留塩素を除去するための試薬の変更• 試料の前処理方法(固相カラムの種類や試料の濃縮倍率)等の変更 | 添加試料の評価のみ | 標準液も試料と同様に前処理を行う検査法の場合は、前処理方法の変更により検量線の作成方法に影響するため、検量線の評価も行う必要がある |
| 測定条件の変更 | • カラムの温度や流速の変更• 質量分析における定量イオンの変更• キャリアーガス、パージガスの変更 | 検量線と添加試料の評価の両方 | 感度、ピーク形状等に影響を与え、定量結果にも影響を与える可能性があるため |
| 検査室の移転 | • 検査室の移転 | 検量線と添加試料の評価の両方 | 検査結果に影響を与えるおそれがない場合に限り評価を省略することができるが、移転前と比べて装置性能が同等以上か、試験環境に由来するブランクレベルが十分に低いかどうか等を確認してから判断する必要がある |
| その他 | • 機器のチューニング• 検査担当者の変更等 | 必要なし | 試験操作や試験環境の変化が生じないと考えられるため |