|
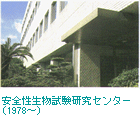 昭和60年(1985年)以後、新剤形医薬品や組み換えDNA医薬品のほか、医用材料、新開発食品、天然添加物など新たに評価の必要な対象物質が生まれてきた。さらに、安全性評価のための新しいリスクアセスメントが必要となった。
昭和60年(1985年)以後、新剤形医薬品や組み換えDNA医薬品のほか、医用材料、新開発食品、天然添加物など新たに評価の必要な対象物質が生まれてきた。さらに、安全性評価のための新しいリスクアセスメントが必要となった。
平成9年7月、医薬品等の承認審査等薬事行政全般の見直しが行われ、国立衛生試験所から国立医薬品食品衛生研究所に改称するとともに、医薬品等の承認等審査を行う医薬品医療機器審査センターを新設した。
平成14年4月、食品関連部門を統合するなど国立試験研究機関の再構築を行い、伊豆薬用植物栽培試験場を廃止し、新たに遺伝子細胞医薬部、食品衛生管理部、医薬安全科学部の3部を設置した。
平成16年4月、ゲノム科学等を応用した画期的な医薬品開発等の基盤となる研究を行うため、大阪支所の組織を改編し、大阪府茨木市に移転した。
また、医薬品医療機器審査センターは、医薬品等の承認審査等の業務を一元化するため、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構に統合された。
平成17年4月、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤技術を図ることとして、国立研究開発法人 医薬基盤研究所が設置され、細胞バンク部門、大阪支所及び薬用植物栽培試験場(北海道、筑波、和歌山、種子島)が移管された。
平成29年10月、世田谷区用賀の庁舎より川崎市殿町にあるライフサイエンス・環境分野における最先端企業や研究機関が集結した国際戦略拠点「キングスカイフロント」に移転した。
これらにより、世界的な視野に立った活力ある試験・研究を行うとともに、関連分野における国際協力を支える機関としての責任を果たしている。
|