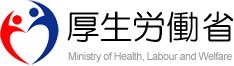■ 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法 質疑応答集 (Q&A)
令和5年3月24日公開,令和5年9月22日更新,令和6年3月21日更新
厚生労働省水道課 国立医薬品食品衛生研究所
(本ページのPDF版はこちら )
)
1. 試薬
- Q1-1)試薬の調製量は、各別表で示された調製量と同量を調製しなければならないのか。
- A1-1)試薬のうち調製量が定められているものは、各別表に定めるものと同濃度であれば、各別表に定める調製量以上に調製することができる。
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」
 における総則的事項2⑶を参照されたい。
における総則的事項2⑶を参照されたい。
2. 器具及び装置
- Q2-1)可視吸収検出器、紫外部吸収検出器、フォトダイオードアレイ検出器、蛍光検出器、分光光度計又は光電光度計を用いる検査方法の一部(別表第12、第18、第19の2、第24、第28、第28の2、第36及び第39)において、検出器の設定波長の値に「付近」が付されているが、この「付近」とはどのように解釈すればよいか。
- A2-1)これらの別表においてその付近とした検出器の設定波長の値については、原則として指定値を設定するものとするが、妨害物質等の影響が軽減され、より精度の高い測定が可能となる場合に限り、指定値の付近の値を設定することができるものであること。
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について」(平成29年3月28日付け生食水発0328第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
- Q2-2)試薬の調製及び検量線の作成に当たり、メスフラスコの容量が規定されていない場合には、極めて少量(例えば1ml)のメスフラスコを使用して差し支えないか。
- A2-2)メスフラスコの容量が規定されていない場合には、原則としてJIS規格のメスフラスコの最小容量である5ml以上のものを使用すること。
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について」(令和6年3月21日付け健生水発0321第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
3. 試料の採取及び保存
- Q3-1)別表第19、第19の2、第19の3、第29及び第29の2において、採水容器のアセトン洗浄を行ってよいか。
- A3-1)これらの別表においては、精製水のみによる洗浄でもホルムアルデヒドやフェノール類が採水容器に残留しないことが確認できたことからアセトン洗浄を消除したものであり、アセトン洗浄を行うことは差し支えない。
「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正等における留意事項について」(令和6年3月21日付け健生水発0321第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
4. 試験操作
- Q4-1)水質基準項目の定量下限は、各別表に示された対象物質の濃度範囲の下限と同一濃度にしなければならないのか。
- A4-1)水質基準項目の定量下限は、各別表に示された対象物質の濃度範囲の下限と同一濃度でなくても差し支えないが、原則として基準値の10分の1以下とすること。ただし、非イオン界面活性剤の固相抽出―吸光光度法(別表第28)の定量下限は原則として基準値の4分の1(0.005 mg/L)以下とすること。
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(平成15年10月10日付け健水発第1010001号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
- Q4-2)複数の成分を合算して評価する項目について、各成分の定量下限はどのように設定すればよいか。
- A4-2)複数の成分を合算して評価する項目の場合は、各成分が基準値の1/10以下の濃度になるように定量下限を設定すること。
「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて」(平成24年9月6日付け健水発0906第1~4号、最終改正:平成29年10月18日付け薬生水発1018第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
- Q4-3)ジェオスミン及び2―メチルイソボルネオールのパージ・トラップ―ガスクロマトグラフ―質量分析法(別表第25)において、塩析の操作を行ってもよいか。
- A4-3)別表第25においては、塩析の操作を行っても差し支えない。
- Q4-4)ガスクロマトグラフ―質量分析法の一部(別表第25、第26、第27及び第27の2)において、検査に用いるフラグメントイオンが例として示されているが、ここに示されたフラグメントイオン以外を使用してもよいか。
- A4-4)これらの別表において、フラグメントイオンは例として示しているため、妥当性評価ガイドラインに基づく妥当性評価を実施した上で、示されたもの以外のフラグメントイオンを用いることは差し支えない。
「「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正について」の留意事項について」(令和5年3月24日付け薬生水発0324第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
- Q4-5)液体クロマトグラフ―質量分析法(別表第17の2、第18の2、第19の3、第24の2及び第29の2)において、検査に用いるモニタ―イオンが例として示されているが、ここに示されたモニターイオン以外を使用してもよいか。
- A4-5)妥当性評価ガイドラインに基づく妥当性評価を実施した上で、示されたもの以外のモニターイオンを用いることは差し支えない。
- Q4-6)陰イオン界面活性剤の液体クロマトグラフ―質量分析法(別表第24の2)において、内部標準液の添加を省略できる条件は何か。
- A4-6)別表第24の2において内部標準液の添加を省略する場合には、検査対象となる水道水等を用いて、妥当性評価ガイドラインに基づく添加試料の試験で選択性、真度、併行精度の目標を満たしていることを確認すること。この際、検査方法の精度が硬度などの夾雑成分に影響されやすいことに留意すること。
「「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法等の一部改正について」の留意事項について」(令和5年3月24日付け薬生水発0324第1~4号)
 を参照されたい。
を参照されたい。
5. 検量線の作成
- Q5-1)検量線の作成に当たり、「濃度を段階的にした溶液を調製する」と規定されているものがあるが、どのように濃度を段階的にした溶液を調製すればよいのか。
- A5-1)濃度を段階的にした溶液の調製方法として、同一の容量のメスフラスコを使用して標準液を段階的に加えることで調製する方法や、異なる容量のメスフラスコを使用して標準液を一定量もしくは段階的な容量を加えることで調製する方法がある。
6. 空試験
該当なし7. 連続試験を実施する場合の措置
- Q7-1)オートサンプラーを用いて10以上の試料の試験を連続的に実施する場合には、濃度既知溶液の差し込み試験を行うと規定されているが、その調製濃度はどのように設定すればよいか。
- A7-1)差し込み試験は機器の精度を確認するものであることから、調製濃度の目安としては、当該試験における検量線の濃度範囲の中央値付近とすることを原則とする。
- Q7-2)上記において、10未満の試料の場合は差し込み試験を行う必要があるのか。
- A7-2)差し込み試験が機器の精度を確認するものであることから、オートサンプラーを用いて10未満の試料を連続して試験する場合には、最後の試料の後に同様の確認を行うことが望ましい。