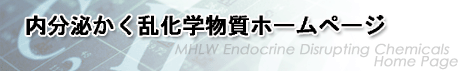|
ウ In vivo スクリーニング試験(③)
さらに、上記の①in silico、及び②in vitro
の系において認定されたホルモン活性が実際の生体内において発揮されるか否かを検討するスクリーニング試験法には、エストロゲン様作用を発揮する化合物に関する試験系として子宮肥大試験、アンドロゲン様物質
に関する試験系としてハーシュバーガー試験を検討した。その結果、前者については既存化学物質や食品関連物質27化合物、後者についても5
物質に関する試験が終了している。3
また、OECD テストガイドライン407(28
日間反復投与試験)の改良版についても、甲状腺系などを考慮したスクリーニングとしての有用性の検討を行った。3
ガイドライン及び評価基準の整備に関しては、②同様、既に何らかの内分泌学的生体影響が自然、実験を問わず報告されている化学物質を当面の陽性対象物質群として、それらの生体影響の機序、あるいは、影響の強度が十分な精度で観測可能であることをスクリーニング試験法の評価基準としている。そして、実験手法の内、この評価基準を満たすものを、国際的・国内的なバリデーション(有効性確認)、あるいはその前段階のプレ・バリデーションの対象となる手法としてガイドライン化を念頭に提案している。
(2)「優先リスト」4
スクリーニング試験で述べた各試験についての結果を基に、優先リストの成熟化(データの蓄積)が進められている。5
(3)確定試験(詳細試験)
詳細試験に関しては、従来の多世代繁殖毒性試験の限界を認識し、その改良を含む試験法の開発が進められている。これは、具体的には、一生涯(発生、発達、成熟、老化)のすべての段階において内分泌かく乱作用により懸念される毒性指標(神経・行動、免疫毒性等、高次生命系及びその成熟に対する障害(図)に焦点を当てた、従来の多世代繁殖試験の指標に限定されない一連の指標)を網羅的に確認する「げっ歯類一生涯試験法」である。
神経・行動に関しては、Bisphenol A 妊娠期・授乳期暴露をモデルとし、dopamine及びserotonin
(5-HT)神経系に着目した行動影響の評価と機序、マウス・オペラント条件付けによる神経系高次機能影響の評価及び脳の性分化への影響解析が行われている。
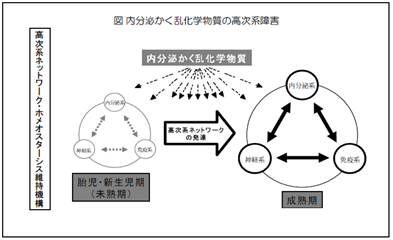
クリックすると画像が拡大されます。
|