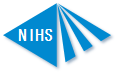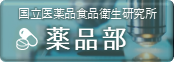(旧称:ジェネリック医薬品品質情報検討会)
議事概要及び公開資料
第33回ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情報検討会
1.開催日時等
日時:令和6年8月29日(木) 14:00-16:30
場所:AP虎ノ門 Room B 及び Web
2.出席者等(敬称略)
出席委員(15名):
本間正充(座長)、宮川政昭、澤木康平、橋場元、東光久、荒戸照世、石井伊都子、伊豆津健一、伊藤清美、大谷壽一、奥田晴宏、田上貴臣、南博信、武藤正樹、渡邊善照
欠席委員 (0名):
参考人:
佐藤岳幸、浅見宗俊(日本ジェネリック製薬協会)、永井祐子(日本バイオシミラー協議会)
事務局:
| 国立医薬品食品衛生研究所: | 国立医薬品食品衛生研究所 齋藤嘉朗(副所長)、佐藤陽治、吉田寛幸、小出達夫、森田時生(薬品部)、石井明子、橋井則貴、柴田寛子、日向昌司(生物薬品部) |
| 国立感染症研究所 : | 鈴木里和(薬剤耐性研究センター)、星野泰隆(真菌部) |
| 厚生労働省 : | 中井清人、宮坂知幸、太田一実 、影山大夢、鈴木翔太(医薬品審査管理課)、中矢雄太、桝田昂志、髙野峻輔(監視指導・麻薬対策課)、安藤駿佑(医薬安全対策課) |
| 医薬品医療機器総合機構 : | 高木和則、佐野幸恵、小川卓巳(ジェネリック医薬品等審査 部)、栗林亮佑、大滝尚広(再生医療製品等審査部)、關野一石、杉浦方紀、木村絵梨、樋口優紀子(安全性情報・企画管理部)) |
3.審議概要
(1)開会
委員15名の出席で開催された。
新委員として田上貴臣委員が紹介された。
(2)第30 回検討会で検討対象となった製剤の溶出試験結果について
第30 回ジェネリック医薬品品質情報検討会(令和5年1月)において選定・了承された9品目(セレコキシブ錠、ブロナンセリン錠、デュロキセチン塩酸塩カプセル、ラモトリギン錠、レベチラセタム錠、クラリスロマイシンドライシロップ、イルベサルタン錠、ジルムロ配合錠
[アジルサルタン/アムロジピンベシル酸塩錠]、メマンチン塩酸塩OD 錠)について製剤試験ワーキンググループ(製剤試験WG)にて、複数試験液を用いた溶出挙動の検討を行い、その結果が報告された(資料33-1)。
ラモトリギン錠小児用5mg については、水を試験液としたとき、1製剤が先発品の溶出挙動と類似の範囲外であった。当該メーカーより、開発時の生物学的同等性試験で使用されたロットと比較したところ類似の範囲にあることが確認された。
クラリスロマイシンドライシロップ10%については、pH 5.5 の試験液において、5製剤の溶出が先発品と比較して速く、類似の範囲外であった。これらの製剤は品質再評価後に開発されたもので、開発・申請時には『後発品の生物学的同等性試験ガイドライン』に従い、pH 5.0 の試験液を用いて溶出試験を実施しており、pH 5.5 の溶出挙動は評価されていなかった。3社からは、自社で実施したpH 5.0 またはpH 5.5 溶出試験結果に基づき品質に問題がないことが報告された。残る2社については、pH 5.0 またはpH 5.5 の試験結果を次回提出し、溶出挙動を確認することとなった。
メマンチン塩酸塩OD錠20mg については、複数の試験液で1製剤の溶出が遅く、先発品と類似の範囲外であった。当該メーカーより、当該ロットは溶出規格を満たしていること、また製剤試験
WG での分析法とメーカーの分析法の差異が結果に影響した可能性があることが説明された。溶出挙動が非類似であった試験液については、今後溶出挙動の確認を行うことが報告された。
委員より、本検討会の資料中のグラフ等について、共同開発品を識別できる表記にすることが提案され、次回から表記方法を工夫することとなった。
さらに、溶出初期(5~10分)の溶出挙動の違いがヒトの吸収速度に影響を与える可能性について懸念が示された。事務局より、溶出初期に差異はあるものの、15分以降の溶出は同程度の溶出であり、小腸以降での薬物吸収に大きな差異は生じないと考えられること、また、ヒト生物学的同等性試験で
Cmax の同等性を確認することで、これら溶出の差異が実際に吸収速度に影響していないと評価されていることが説明された。
以上の内容について確認され、了承された。
(3)製剤試験WG において検討した製剤の再試験結果
第23回ジェネリック医薬品品質情報検討会(令和元年11月)において品質課題が指摘され、企業による品質改善が実施されたテルミサルタン錠の再試験結果が報告された。いずれの製剤も先発品またはオレンジブックの溶出と類似の範囲にあり、適切な改善がなされていることが確認された(資料33-2)。
以上の内容について確認され、了承された。
(4)学会等での発表・研究論文について
後発医薬品及びバイオシミラーに関して、令和5年度下半期の文献及び学会発表(資料33-3、資料33-4)について報告された。
ケトプロフェンテープ剤の先発品・後発品間の貼付後の残存率の比較、およびツロブテロールテープ剤における膜透過速度の先発品・後発品間の差に関する学会報告について、委員より、承認時の生物学的同等性の評価方法が確認された。事務局より、いずれの製剤もヒトにおいて有効性試験、または血中濃度を指標としたヒト生物学的同等性試験が実施され、承認されていることが説明された。
委員より、プレガバリンOD錠の硬度評価については、同一条件で横並びの評価を行うことが有用であるものの、錠剤硬度測定法は測定方法の影響を大きく受けるため、試験条件を確認する必要があるとの意見があった。
バイオシミラーに関する問題指摘文献について議論がなされた結果、検討会で追加の検証が必要な事項は特にないものの、今後も品質および安全性に関する情報の収集に努めることが確認された。
以上の内容について、確認され了承された。
(5)(独)医薬品医療機器総合機構の後発医薬品相談窓口相談について
令和5年度下半期の医薬品医療機器総合機構への相談内容について報告された(資料33-5)。
委員より、これまでも「貼付剤がはがれやすい」という相談が多く寄せられていることを受け、貼付剤の承認要件として、米国で検討されているヒトでの粘着性評価の導入を検討してはどうかとの意見が出された。また、現在各企業が設定している粘着性の規格試験についても、日本薬局方の一般試験法で規定されている粘着力試験法(4種の試験法)の何れかを製販各社が選択しているため、各社間で試験法が異なることや、日本薬局方で規定されている温度や湿度などの試験条件が実際の使用環境を反映していないことから、より適切な条件設定が必要ではないかとの指摘があった。この問題について、今後、厚労省を中心に検討を進めることとなった。さらに、事務局より、既承認の貼付剤についても、粘着力および放出性の試験を実施する方針であることが説明された。
以上の内容について、確認され了承された。
(6)その他
事務局より、第29回検討会で報告された、球形吸着炭製剤の品質等に係る報告書について、報告資料に記載の規格及び試験方法(資料29-6 別添3)に誤記があったことが報告され、訂正された。
委員より、後発品の問題を指摘する文献報告等は年々減少しているものの、問題自体が無くなったわけではないと考えられることから、潜在的な問題を検出する新たな方法を検討する必要があるとの意見が出された。
4.提出資料
| 資料名 | ||
|---|---|---|
| 1 | 議事次第 | |
| 2 | ジェネリック医薬品・バイオシミラー品質情報検討会メンバー | |
| 3 | 資料33-1 第30 回検討会で検討対象となった製剤の溶出試験結果 | |
| 4 | 資料33-2 製剤試験WG において検討した製剤の再試験結果 | |
| 5 | 資料33-3-1 後発医薬品文献調査報告書(概要) | |
| 6 | 資料33-3-2 後発医薬品文献調査結果のまとめ | |
| 7 | 資料33-3-3 後発医薬品問題指摘論文集(著作権の関係で掲載できません) | |
| 8 | 資料33-4-1 バイオシミラー文献調査報告書(概要) | |
| 9 | 資料33-4-2 バイオシミラー文献調査結果のまとめ | |
| 10 | 資料33-4-3 バイオシミラー問題指摘論文集(著作権の関係で掲載できません) | |
| 11 | 資料33-5 医薬品医療機器総合機構後発医薬品相談受付状況 | |
| 12 | 参考資料1 資料29-6 別添3 各社より改めて提案された規格及び試験方法(案)の修正 (承認情報を含むため非公開) |