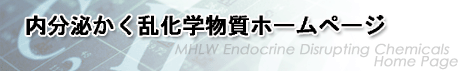|
|
内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会
中間報告書追補その2 |
| |
目次 詳細目次 <<前 次>> |
| 第1章 |
重点課題の検討成果と今後の取組 |
| 第1節 |
試験スキーム |
| |
1.はじめに
厚生労働省では、内分泌かく乱性を検討する必要がある数万種の対象化学物質について、ホルモン活性に焦点を置いたスクリーニング手法の開発と確立を進め、もって、確定試験(詳細試験)に資する優先リストの作成を進めると同時に、詳細試験の開発を並行して行うこととされ(下図)、各試験の開発研究が行われてきた。
|
| |
2.試験スキーム(拡張版)の概要 |
スクリーニングについては、図の①、②および③の手法をバッテリーとして適応することにより、数十万種類の検討対象化学物質のホルモン活性を順次調べることが可能となり、その結果を基に、詳細試験に資するべき物質の優先リストが提供される。
優先リストは
、新しい情報やスクリーニング試験結果が得られると、逐次ソーティング(並べ替え)(例えば、ホルモン活性が強い結果が得られると上位に、また、弱い結果が得られれば下位に当該化学物質の位置は移動する。)が行われることにより時間と共に、その内部構造が成熟していく。また、暴露量の知見等、スクリーニング試験結果以外の情報を加味することが可能であり、包括的な優先順位付けが行われる。 |
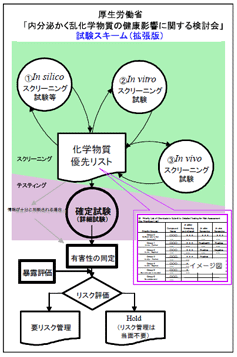
クリックすると画像が拡大します。 |
| 優先リスト上位の化合物から逐次、詳細試験を行い、有害性評価、暴露評価を経て、リスク評価を行い、「要リスク管理」物質及び「リスク管理は当面不要」物質にふるい分けられ、後者については新たな科学的知見により再評価が必要となるまで、暫定的にholdされる。(例外として、農薬等、多世代試験などの大型詳細試験がすでに実施されている物質については、そのデータが内分泌かく乱性の評価に十分であると考えられた場合について、直ちに有害性評価、暴露評価、リスク評価へと進むことができる) |
|
目次 詳細目次 <<前 次>> |