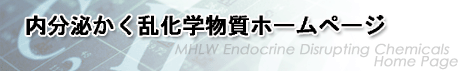| |
10)計算
・計算工程の記録:標準溶液の濃度、内部標準の添加量、機器測定面積値、試料採取量から最終濃度算出までの計算工程がトレース可能となる記録を残す。
・回収率の確認・記録:回収率を記録する。回収率は、70〜120%の範囲であることが望ましい。
11)ブランク試験
・採取器具、採取容器、運搬・保存容器等についてブランク試験を行い、その結果を記録する。
・試薬類のブランク試験を行い、その結果を記録する。このブランク試験は試薬類のロット番号が変わるごとに行う。
・全操作ブランク:試料に対して行う分析方法と同一の方法で操作を行い、その結果を全操作ブランクとして記録する。
12)2 重測定
分析検体数10 に対して1 以上の頻度で行うことが望ましい。この2
重測定の結果は各実測値の差が30%以内であることが望ましい(実測値が目標定量下限値の10 倍以下の化合物に関しては規定しない)。
13)外部機関とのインターキャリブレーションを行うことが望ましい。7.その他
食品衛生法「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱」参照。
飼料分析基準研究会 編著、飼料分析法・解説-2004-、社団法人 日本科学飼料協会 参照。 |