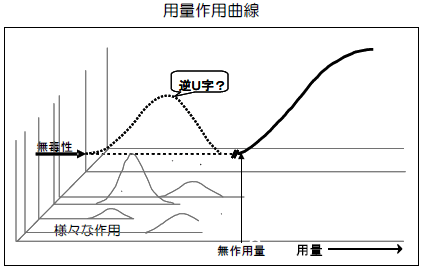
|
|
|
|
毒性試験では、生物に与える化学物質の有害作用は、用量が多くなるほど強くなる傾向にあります(図の太線カーブ)。通常の化学物質の生体影響の観察は、このカーブの大量に暴露した時に得られたデータから、低用量での影響を予測する方法をとってきました。しかし、内分泌かく乱化学物質として疑われている物質では、Q3でも触れたとおり、生理的レベルと毒性レベルの境界領域の影響を検討の対象としているため、その影響が必ずしも用量に伴って増加しない場合があることが分かってきました。例えば、ホルモン様の作用物質の中には、高用量では作用が見られず、至適濃度をピークとした様々な作用が低用量域で観察されることがあります(図左下の小さな小山)。ところが、図の点線カーブ(逆U字型になる部分が見られることから「逆U字効果」と呼ばれました)で示したような、これまで知られている「無作用量」よりも少ない量で影響が見られるとなると、大量に暴露して得られたデータから、低用量での影響を予測することが出来ないことになります。そこで様々の研究が行われ、いま、特に無作用量以下で見られるこれらの諸作用のひとつひとつに生体への傷害性があるかどうかについての検討がすすめられています。点線で示した逆U字効果のような事も起こるのかどうかが調べられています。低用量問題の検討は、もう少し時間がかかりそうです。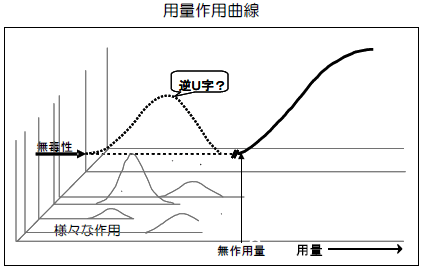 |