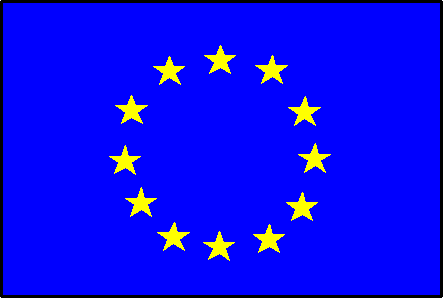ICSCに出てくる用語
分子量の表記
ICSC(英語原文)中では、銅、ヒ素など元素の場合はAtomic Mass、その他の化合物の場合は、塩化アンモニウム、塩化バリウムなどの無機塩類も含め、Molecular Mass と表記している。無機塩類等の場合は正確には式量と表記すべきものであるが、日本語版では便宜上ICSC原文にならって、原子量(Atomic Mass)及び分子量(Molecular Mass)で表記する。
引火点の項のC.CとO.C
引火点(flash point)の項で数値のうしろに(C.C.)および(O.C.)が付記されている場合があるが、これらは引火点を測定する方法で、C.C.はclosed cup、O.C.はopen cupのこと。
log Pow (オクタノール/水分配係数)
オクタノールと水の混合物に物質を溶解させたときのオクタノールと水中の物質濃度の比をオクタノール/水分配係数といい、Powで表す。便宜上、常用対数値log Powで示されることが多い。この値が大きいほど油脂に親和性がある。水生生物における生物蓄積性等環境中での挙動を予測する上で有用である。
許容濃度の項目
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
米国産業衛生専門家会議などと訳されるが通常ACGIHのままで使われている。米国の産業衛生の専門家の組織。化学物質等の職業的許容濃度の勧告値や化学物質の発がん性の分類を公表しているが、その値は世界的に重要視されている。
TLV (Threshold Limit Values)
ACGIHでは労働者が作業環境中で暴露される大気中の化学物質の許容濃度 (TLV)等を設定し、毎年改訂して発表している。TLVは、毎日繰り返しある物質に暴露したときほとんどの労働者に悪影響がみられないと思われる大気中の濃度をいう。TLVには次のようなものがある:
- TWA (Time Weighted Average:時間加重平均値、時間荷重平均値)
- 毎日繰り返し曝露したときほとんどの労働者に悪影響がみられないような大気中の物質濃度の時間加重平均値で、通常、労働時間が8時間/日及び40時間/週での値。作業環境中で大気中の物質濃度は一日のうちに変動し得るが、TWAは濃度とその持続時間の積の総和を総時間数で割ったものである。
- STEL (Short Term Exposure Limit:短時間暴露限界値)
- たとえTWAが許容範囲内であっても、労働者が作業中の任意の時間にこの値を超えて暴露してはならない15分間の時間加重平均値。STELが設定されている場合の暴露は、15分を超えて続いてはならず、また一日4回以内でそれぞれの間に60分以上の間隔がなければならない。短時間に高濃度の物質に暴露したとき毒性影響がみられるような場合等に用いられる。
- 天井値 (Ceiling value、TLV-C)
- 作業中のどの時点においても超えてはならない値。
- Skin(皮膚)の表示があるもの
- 粘膜や眼を含め経皮吸収の可能性があるものについては数値のうしろに(皮膚)の表示がある。
- TLVは設定されていない
- TLVが設定されている物質の数はまださほど多くはなく、「TLVは設定されていない」と記載されていても、この物質が安全であるという意味ではない。
国連危険物分類
国連の「危険物輸送に関する勧告」(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)では、危険物を大きく9クラス(class)に分類している。これらはさらにいくつかの区分(division)に分けられている。たとえば、分類 6.1は毒物であり、8は腐食性物質である。
この勧告を収載している印刷物(UN Model Regulations)は、通称オレンジブックと呼ばれており、現在第24改訂版が出ている。
- クラス1: 爆発物 (Explosives)
- 区分1.1: 大量爆発の危険がある物質または物品
- 区分1.2: 大量爆発のおそれはないが、飛散の危険がある物質または物品
- 区分1.3: 大量爆発のおそれはないが火災の危険があり、かつ小規模な爆風か飛散もしくはその両方の危険がある物質または物品
- 区分1.4: 発火時に大規模な危険性が認められない物質または物品
- 区分1.5: 大量爆発の危険性があるが、通常の輸送条件下では鈍感な物質
- 区分1.6: 大量爆発の危険がなく、非常に鈍感な物質
- クラス2: 高圧ガス (Gases)
- 区分2.1: 引火性ガス
- 区分2.2: 非引火性の無毒ガス
- 区分2.3: 有毒ガス
- クラス3: 引火性液体 (Flammable liquids)
- クラス4: 可燃性固体、自然発火性物質、水と反応して可燃性ガスを発生する物質 (Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion;
Substances which in contact with water emit flammable gases.)
- 区分4.1: 可燃性固体
- 区分4.2: 自然発火性物質
- 区分4.3: 水と反応して可燃性ガスを発生する物質
- クラス5: 酸化性物質; 有機過酸化物 (Oxidizing substances; organic peroxides)
- 区分5.1: 酸化性物質
- 区分5.2: 有機過酸化物
- クラス6: 毒物、感染性物質 (Toxic and infectious substances)
- 区分6.1: 毒物
- 区分6.2: 感染性物質
- クラス7: 放射性物質 (Radioactive material)
- クラス8: 腐食性物質 (Corrosive substances)
- クラス9: その他の危険物 (Miscellaneous dangerous substances and articles)
環境毒性の基準
環境毒性の項目で使用されている標準語句「この物質は水生生物に.....。」の原文は次のとおりである。
The substance is [ ] to aquatic organisms.
[ ] の中には、その物質の魚毒性等の強さに応じて "very toxic"、 "toxic"、 "harmful" を記入する。たとえば魚類に対する LC50 (96時間)が得られている物質の場合、この3種の語句の選択基準は次のとおりである。
| 標準語句 | 和訳 | 選択基準 |
|---|---|---|
| very toxic | 毒性が非常に強い | LC50 ≦ 1 mg/l |
| toxic | 毒性が強い | 1 mg/l < LC50 ≦ 10 mg/l |
| harmful | 毒性がある | 10 mg/l < LC50 ≦ 100 mg/l |
(注)この基準は、あくまでICSCにおける選択基準です。